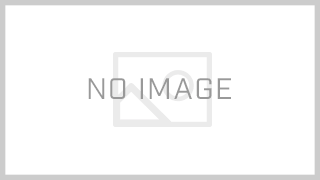朝・昼・夕の1日3回の食事は、規則正しいリズムで取ることにより体内時計を調整することができる。
特に、朝食は体内時計のリセットに重要な役割があり、視交叉上核に太陽の光が屠蘇いてから1時間以内に食事をすることによって主時計と末梢神経が連動して働くようになるといわれている。
まずは朝食の見直しを、考えてみよう!
朝食の欠食による影響は、次の4つのものが挙げられます。
① 体内時計の乱れ
② 肥満
③ 筋肉量の減少
④ 脳機能の低下
① 朝食の欠食による影響
② まとめ
① 朝食の欠食による影響
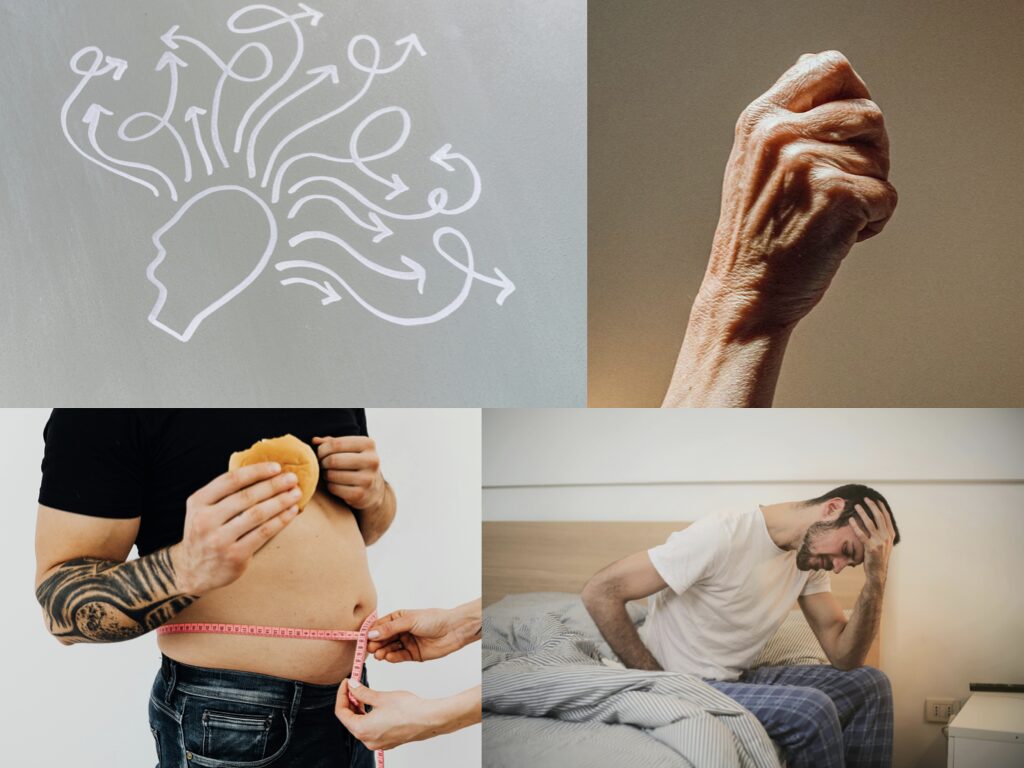
朝食の欠食による影響は、次のものが挙げられます。
① 体内時計の乱れ
② 肥満につながる
③ 筋肉量の減少
④ 脳機能の低下
① 体内時計の乱れ
私たちの体は寝ている間もエネルギーを使っている。
朝は、エネルギーが不足しているため、朝食で必要なエネルギーや栄養素を補い、活動するための準備をする。
しかし、朝食を欠食すると体がなかなか活動モードにならないだけでなく、昼食を取った時点で末梢時計がリセットされることになるため、体内時計を乱す原因になる。
② 肥満につながる
人間の体はエネルギー不足状態になると、活動をできるだけ抑えて脂肪の合成を促進する。
また、朝食の欠食による血糖値の低下で食欲が亢進し、昼食や夕食を多く取る傾向がある。
一度にたくさん食べると、急激な血糖値の上昇が起こり、インスリンを過剰に分泌し血糖を脂肪に変えてしまう。
また、朝食欠食者は体温が低く、エネルギー代謝が低下する傾向があり、この点も肥満になりやすい原因となる。
③ 筋肉量の減少
低血糖状態では、脳にブドウ糖を送り込もうとして、筋肉内のタンパク質を分解する糖新生反応が起こる。
糖新生が長く続くと筋肉量が減少していく。
文部科学省の「体力・運動能力調査」では、朝食欠食児は朝食摂食児より男女ともに体力が低いことが分かっている。
④ 脳機能の低下
ブドウ糖は脳のエネルギー源となるが、脳内に貯蔵しておくことができない。
脳がエネルギー不足になると、脳の働きも鈍くなり、集中力、活力、記憶力、思考能力などの低下につながる。
文学科学省の全国学力・学習状況調査では、朝食を食べている児童や生徒の方が学業成績が優れていることが分かっている。
② まとめ

毎日の食事、特に朝食が体のコンディションを整えていることが、改めてわかります!
体内時計や筋肉、まさかの脳まで関係するなんて、想像もしないですよね!
運動する中でも、フィジカル(身体)もメンタル(精神的)も、毎日の食習慣から見直す必要があります。
特に、これから運動で上を目指すなら尚更!
1日も早く、この食の大切さに気づけた方はとてもラッキーですね!
毎日、1日3食しっかり食べて、100%の力を毎日確実に出せる体づくりをしていきましょう!