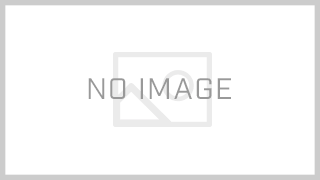脂質と聞くと、「脂肪」とふっくら太って運動するのに必要なないものに感じる人がいます。
だが、脂質はエネルギー源や細胞膜、核酸、神経組織などの主要な構成成分であり、脂質が不足することで、エネルギー不足、細胞膜や血管壁の弱まりに繋がります。
そのため、極端に脂質制限をすることで、運動に悪影響が出てしまいます。
改めて、脂質というものがどのような働きでどのようなものかを知っていってほしいです。
かなり、誤解をしている人もいると思います!
① 脂質の分類
② 脂肪酸の種類
③ トランス脂肪酸
④ コレステロール
⑤ まとめ
① 脂質の分類、特徴

脂質は、中性脂肪(トリグリセライド)、脂肪酸、コレステロール、リン脂質の4つに分けられる。脂質の働きは、種類によって異なる。
| 種類 | 主な働き |
|---|---|
| 中性脂肪 (トリグラセライド) | ・エネルギー源になる ・体温を一定に保ち、臓器などを守る |
| 脂肪酸 | ・エネルギー源になる ・細胞膜の構成成分になる |
| コレステロール | ・細胞膜の構成成分になる ・ホルモンの材料になる ・胆汁酸の材料になる |
| リン脂質 | ・細胞膜の構成成分になる ・中性脂肪やコレステロールを血液や胆汁に馴染ませて運搬する |
肉類や油脂類、魚介類、乳製品に多く含まれる。
脂質を取りすぎると、エネルギーの取り過ぎにつながり、肥満や脂質異常症の原因となります。
また脂質が不足すると、エネルギー不足で疲れやすくなり、脂溶性ビタミンの吸収が悪くなり、肌荒れや便秘、ホルモンの機能などの体の機能にも影響します。
② 脂肪酸の種類

中性脂肪に(トリグリセライド)には脂肪酸が含まれるが、その脂肪酸の種類によって体内での働きや代謝の仕方が異なる。
脂質を体調維持に役立てる場合には、その「量」と「質」に配慮することが大切であり、その質を決めるのは脂肪酸である。
ー脂肪酸の種類ー
| 分類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 飽和脂肪酸 | ・常温で固体 ・酸化されにくい ・血中中性脂肪、血中LDLコレステロールの上昇 |
| 不飽和脂肪酸 ・一価不飽和脂肪酸 (n-9、オメガ9脂肪酸) ・n-6系脂肪酸 (オメガ6脂肪酸) ・n-3系脂肪酸 (オメガ3脂肪酸) | ・常温で液体 ・酸化されやすい ・血中LDLコレステロールの低下 |
《飽和脂肪酸》
飽和脂肪酸を多く含む脂質は、融点(固体が融解する温度)が高いため、常温でも固体であることが多い。
重要なエネルギー源であるが、過剰摂取は控え、不飽和脂肪酸との摂取比率を良好なものとする必要がある。
また不飽和脂肪酸に比べ、酸化されにくいという特徴がある。
●体内での働き
| ① エネルギー源になる |
| ② 中性脂肪(トリグリセライド)をつくる 中性脂肪(トリグリセライド)中で飽和脂肪酸の割合が増えると、血液の粘度が高まる |
| ③ コレステロールをつくる 血中コレステロールの70〜80%は体内で合成されるが、飽和脂肪酸はその原料になる |
飽和脂肪酸を取り過ぎると、体内での中性脂肪・コレステロールの合成が進み、血中脂質を増やす。
動脈硬化を促進させ、心筋梗塞などの原因になる。
飽和脂肪酸が多く含まれる食品は、肉類や油脂類(バターなど)、乳製品などに多く含まれているので、取りすぎに注意しよう。
《不飽和脂肪酸》
不飽和脂肪酸を多く含む脂質は、融点が低いため、常温では液体で存在する。
また飽和脂肪酸に比べ、酸化されやすいという特徴がある。
●体内での働き
不飽和脂肪酸の働きは、種類により異なる。
| 種類 | 主な脂肪酸 | 主な働き |
|---|---|---|
| 一価不飽和脂肪酸 (n-9系脂肪酸) (オメガ9脂肪酸) | オレイン酸 | ・血中LDLコレステロール低下作用 ・酸化されやすい |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6脂肪酸) | リノール酸 アラキドン酸 | ・血中LDLコレステロール低下作用 ・一価不飽和脂肪酸より酸化されやすい ・リノール酸の過剰摂取によるリスクに注意する |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3脂肪酸) | α-リノレン酸 EPA DHA | ・血中LDLコレステロール低下作用 ・一価不飽和脂肪酸より酸化されやすい ・EPAおよびDHAは心疾患や脳卒中、糖尿病、 乳がん、大腸がん、肝がん、加齢黄斑変性、 認知障害、うつ病などの予防効果の可能性が あり |
不飽和脂肪酸の取り過ぎは、エネルギー源である脂質の一部であるため、過剰摂取は肥満の原因になる。
また、n-6系脂肪酸のリノール酸は酸化しやすさや炎症作用などがあるため、過剰摂取は心筋梗塞の罹患を増やすなどの危険がある。
不飽和脂肪酸の不足は、n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸は、体内で合成できないため、不足すると、皮膚炎などが発症する。
一価不飽和脂肪酸を多く含む食品は、オリーブ油やサフラワー油。
n-6系脂肪酸を多く含む食品は、ごま油や種実類、大豆などに多く含まれる。
n-3系脂肪酸を多く含む食品は、魚介類(マグロ、ぶり、イワシ、さばなど)や亜麻仁油、エゴマ油。
不足ないように、意識して不飽和脂肪酸の含む食品を摂るようにしよう!
③ トランス脂肪酸

ここで日本で生活する人は、注意が必要な、脂肪酸がある!
それが「トランス脂肪酸」だ!
トランス脂肪酸の取り過ぎは、血中LDLコレステロールが増加し、心臓病のリスクを高めるという報告がある。
トランス脂肪酸の多くは、マーガリンやショートニングなどの加工油脂やこれらを原料に使ったパンやケーキ、スナック菓子、ファストフードの揚げ物、レトルト食品などに多く含まれる。
トランス脂肪酸量は諸外国では規制がかかっているが、日本においては特別な規定はない。
そのため、日本で住んでいる方のほとんどはトランス脂肪酸を摂取していることになる。
運動する上で、健康な体を作るためには、絶対に注意が必要な脂肪酸です。
④ コレステロール

コレステロールは、全身にあるすべての細胞膜の構成成分であり、コレステロールがなければ、細胞は崩れてしまいます。
●体内での働き
| ① 細胞膜をつくる すべての細胞の細胞膜に存在し、膜の流動性を調節をする |
| ② 胆汁酸をつくる 脂質の消化に不可欠な胆汁酸の材料であり、脂質を溶けやすくするとともに膵臓から出る脂質の消化酵素を活性化し、脂質の消化吸収を助けている |
| ③ ホルモンをつくる 副腎皮質がつくるホルモンや男性ホルモンのアンドロゲン、女性ホルモンのエストロゲン、黄体ホルモンのプロゲステロンなどをつくる |
| ④ ビタミンDをつくる 皮膚に存在するコレステロールがビタミンDの材料となり、これが日光に当たると皮膚でビタミンDがつくられる。 |
コレステロールを取り過ぎると、血中コレステロール値が上がる原因となり、脂質異常症や動脈硬化などの生活習慣病につながる恐れがある。
ただし、血中コレステロールの上昇は、コレステローだけではない。
コレステロールが不足は、通常は体内で合成できるので不足することはないが、低コレステロール血症は、脳出血などの病気を誘発する可能性が示唆されている。
コレステロールの取り過ぎを注意するために、食物繊維と合わせ摂取するといい。
特に海藻や果物に多く含まれる、水溶性食物繊維は吸収を抑える作用が強いと言われている。
⑤ まとめ

脂質は体を構成させるため、動かすために必ず必要な栄養素です。
摂取量を気をつける必要はありますが、必要量取ることで皆さんが運動する時のエネルギーとなり、体が元気に動くことができます。
しかし、脂質=脂肪のイメージがついていて、他の栄養素より摂取していない栄養素でもあります。
改めて、体のエネルギー源であり、強く壊れにくい体にするために必要な「脂質」の栄養素も含めて、食事を意識してみてほしいです!