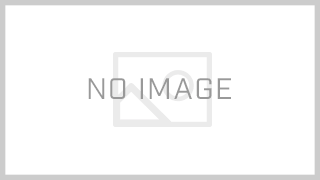ミネラルは、欠乏することで食欲不振や倦怠感、さらにけいれんや心筋障害など体の機能調整に深く関わってきます。
スポーツをする上で、体を動かす際に必ず必要な栄養素となります。
ミネラルとは、体に存在する元素のうち、酸素、炭素、水素、窒素以外のものを指す。
体重に占めるミネラルの割合は約5%であり、残り約95%は炭水化物、タンパク質、脂質、水などの有機化合物の成分である酸素、炭素、水素、窒素が占める。
ミネラルは体内で合成できないので、食事から摂取しなければならない。
また、尿や汗によって、日々一定量が排泄されているため、欠乏症を起こしやすい。
ミネラルの摂取が不足した場合は排泄を抑制し、過剰に摂取した場合は排泄を促進するように腸や腎臓が調整しているが、過剰摂取が長期に渡れば過剰症を起こす可能性もある。
運動する人は汗を人より出すので、ミネラルが足りなくなる人が多いので、ミネラル摂取を意識し、またミネラルの基礎から、体にどのような影響があるのかを学んでいきましょう!
① ミネラルの分類
② ミネラルの特徴
まとめ
① ミネラルの分類

日本人の食事摂取基準では、体内の量が多いものを「多量ミネラル」、少ないものを「微量ミネラル」に分類している。
ーミネラルの種類ー
| 多量ミネラル | ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム リン |
| 微量ミネラル | 鉄 亜鉛 銅 マンガン ヨウ素 セレン クロム モリブデン |
ーミネラル一覧ー
| 種類 | 主な生理作用 | 欠乏症 | 主な食品 |
|---|---|---|---|
| ナトリウム (Na) | ・細胞外液の浸透圧調節 ・筋肉や神経の興奮抑制 | 食欲不振 倦怠感 けいれん 血圧降下 | 食塩 醤油 味噌 |
| カリウム (K) | ・細胞内液の浸透圧調節 ・ナトリウムの再吸収抑制 ・筋肉の収縮 | 脱力感 食欲不振 | 野菜 果物 いも類 |
| カルシウム (Ca) | ・骨や歯の形成 ・血液凝固 ・筋肉の収縮 ・神経の興奮抑制 | 骨の発達障害 骨粗鬆症 神経過敏 | 乳製品 納豆 煮干し 干しえび 小松菜 水菜 |
| マグネシウム (Mg) | ・筋肉の収縮 ・神経の興奮抑制 ・血管拡張 | けいれん 神経過敏 不整脈 | 豆類 種実類 穀類 海藻類 |
| リン (P) | ・骨や歯の形成 ・糖質、脂質、タンパク質の代謝 ・細胞の構成成分 | 骨軟化症 疲労感 | 肉 卵黄 乳製品 大豆製品 加工食品 |
| 鉄 (Fe) | ・赤血球のヘモグロビン構成 ・酸素の運搬と供給 | 鉄欠乏性貧血 | レバー かつお あさり 肉(赤身) 緑黄色野菜 穀類 海藻類 |
| 亜鉛 (Zn) | ・タンパク質、核酸の合成促進 ・酸素の構成成分 | 皮膚炎 月経不順 成長障害 味覚障害 | 牡蠣 牛肉 レバー 納豆 卵 種実類 |
| 銅 (Cu) | ・鉄とヘモグロビンの結合補助 ・鉄の吸収促進 | 貧血 毛髪異常 白血球数減少 成長障害 | レバー 干しえび いか たこ 牡蠣 種実類 納豆 |
| マンガン (Mn) | ・糖質、タンパク質、脂質の代謝 ・骨の代謝 ・抗酸化作用 | 骨の発達障害 生殖能力の低下 | 玄米 くるみ 厚揚げ |
| ヨウ素 (I) | ・甲状腺ホルモンの構成成分 ・発育促進 ・基礎代謝の向上 | 甲状腺腫 | 海藻類 いわし さば |
| セレン (Se) | ・抗酸化作用 ・がんの抑制 | 心筋障害(克山病) | 魚介類 ねぎ そば |
| クロム (Cr) | ・糖質、脂質の代謝 | 糖代謝障害 | 魚介類 海藻類 |
| モリブデン (Mo) | ・尿酸生成の代謝に関与 | 尿酸代謝障害 | レバー 豆類 種実類 穀類 |
② ミネラルの特徴
《多量ミネラル》

○ナトリウム
ナトリウムは、細胞内外のミネラルバランスを保つために不可欠で、成人で体重の約0.15%を占める。
その多くは、細胞外の体液(細胞外液)に含まれており、水分を保持しながら細胞外液や血液循環の量をコントロールしている。
○カリウム
カリウムの多くは細胞内の体液(細胞内液)に含まれており、細胞外液に多いナトリウムと作用し合いながら、細胞の浸透圧の維持や水分の保持をしている。
また、ナトリウムの腎臓での再吸収を抑制し、尿への排せつを促す。
○カルシウム
カルシウムは、体内に最も多く存在するミネラルであり、成人で体重の1〜2%を占める。
このうち約99%は骨や歯などの硬組織に存在している。
残りの約1%は血液、筋肉、神経、酸素などに存在し、血液凝固や筋肉収縮、神経の興奮抑制などに働く。
一般的に、骨密度は20歳前後をピークに減っていく。
強い骨を維持するためには、生涯を通してカルシウムの摂取は欠かせない。
○マグネシウム
体内の存在するマグネシウムのうち、60〜65%は骨に存在し、カルシウムやリンとともに骨を構成しており、残りの35〜40%は筋肉や血液、細胞内に存在する。
マグネシウムは、約300種類以上もの酵素の働きをサポートし、エネルギー産生をスムーズに行うなどの重要な働きに関与する。
また、神経の興奮抑制、血管拡張による血圧降圧作用、筋肉の収縮にも関与する。
○リン
リンは、カルシウムに次いで体内に多く存在するミネラルであり、成人で体重の約1%を占める。
このうち80〜85%はカルシウムやマグネシウムと結合し、骨や歯を形成している。
残りの15〜20%は糖質やタンパク質、脂質の代謝に関与し、細胞膜の構成成分としてあらゆる細胞に存在している。
《微量ミネラル》

○鉄
鉄は、成人の体内に3〜4g程度存在し、そのうち約70%は赤血球の色素であるヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンというタンパク質の構成成分となっている。
これらは「機能鉄」と呼ばれ、肺から取り組んだ酸素を全身の組織に供給する役割を担っている。
残りの約30%の鉄は「貯蔵鉄」として肝臓や骨髄、脾臓、筋肉などに蓄えられ、機能鉄が不足したときに利用される。
○亜鉛
亜鉛は、成人の体内に2〜4g程度存在し、新人代謝やタンパク質の合成、遺伝情報に関与するDNAやRNAの合成、インスリンの合成、免疫反応にかかわる酵素の構成成分となっている。
○銅
銅は、成人の体内に100〜150mg程度存在する。
赤血球のヘモグロビンを生成するために不可欠で、また、鉄の吸収を促進したり酵素の構成成分となって、多くの代謝に関与している。
また、コラーゲンやエラスチンといった、血管や骨を丈夫にする成分をつくるため、動脈硬化や骨粗鬆症を予防する。
○マンガン
マンガンの多くは肝臓や膵臓などの臓器に約10mg程度存在しており、糖質やタンパク質、脂質の代謝に重要な役割を果たしている。
また、骨の代謝にも欠かせない。
抗酸化作用を持つ酵素の成分でもあり、細胞膜の酸化を防ぎ、細胞を維持している。
○ヨウ素
ヨウ素は成人の体内に約10mg程度存在し、そのほとんどは甲状腺に集中し、ホルモンの成分となっている。
甲状腺ホルモンは、基礎代謝を促進したり、酸素の消費量を増加させる。
幼児の場合、成長促進に欠かせない。
○セレン
セレンは成人の体内に約10mg程度しか存在しないが、体内で生成された過酸化物質を分解する酸素の重要な成分として、ビタミンC・Eと同様に老化防止やがんを抑制する働きが注目されている。
○クロム
成人の体内に存在するクロムの量はわずか約2mg程度であるが、糖質や脂質の代謝にかかわる重要なミネラルである。
インスリンの働きを助けて糖尿病を予防したり、血中コレステロール値や中性脂肪値を下げるので、動脈硬化や脂質異常症を予防するのに役立つ。
○モリブデン
モリブデンは、肝臓や腎臓で酵素の働きを助け、尿酸の代謝および糖質や脂質の代謝に関与する。
成人の体内に含まれる量が9mg以下の微量元素である。
まとめ

ミネラルは、体の細胞単位の調整や栄養を運ぶ血液の働き、生命活動に必須な代謝の働きなどとても重要な働きを担っています。
運動する際にも、体の調整がうまくいかない場合、自分の持っている100%の力を発揮することができません。
もしかしたら、今の体にミネラルを摂ることで、今以上に活躍できる人は多いのではないでしょうか!?
現代の食事では、ミネラルはかなり少なく、日本人はみんな不足していると言われています。
一番、栄養素で摂取を意識して欲しいのが「ミネラル」です。
また改めて、自分の食生活を見直して、常に100%の力を出せる体づくりをしてほしいです。