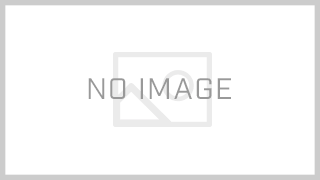ビタミンは、糖質、たんぱく質、脂質のようにエネルギー源や体の構成成分にはならないが、体の機能を正常に維持するために不可欠な物質である。
主に、代謝を円滑にする潤滑油のような働きをしたり、血管や粘膜などの健康を保ち、新陳代謝を促す働きに関与している。
体内ではほとんど合成されないため、食物から摂取しないと、それぞれのビタミンに特有の欠乏症を引き起こす。
スポーツをしている人は、ビタミンやミネラルといった、体の機能を司る栄養素が不足しがちです。
まず今回は、ビタミンの基礎知識を知っていきましょう!
① ビタミンの分類
② ビタミンの特徴
まとめ
① ビタミンの分類

ビタミンは、大きく分けて、水に溶けにくくアルコールや油脂に溶ける性質を持つ「脂容性ビタミン」と水に溶けやすい性質を持つ「水溶性ビタミン」があります。
| 脂容性ビタミン | ビタミンA ビタミンD ビタミンE ビタミンK |
| 水溶性ビタミン | ビタミンB群 ・ビタミンB1 ・ビタミンB2 ・ビタミンB6 ・ビタミンB12 ・パントテン酸 ・葉酸 ・ビオチン ビタミンC |
② ビタミンの特徴
【脂容性ビタミン】

脂溶性ビタミンは」、水に溶けにくく、アルコールや油脂に溶ける性質を持つビタミンでビタミンA・D・E・Kがある。
熱に対して安定しているため、調理による消失が少なく、脂質と併せて取ると吸収されやすいという特徴がある。
脂溶性ビタミンは、食物中の脂質と一緒に小腸から吸収され、主に肝臓へ貯蔵されるため、大量に摂取すると過剰症を起こすものもある。
通常の食生活では取り過ぎる心配はないが、健康食品などで摂取する場合は注意が必要である。
ー脂溶性ビタミン一覧ー
| 種類 | 主な生理作用 | 欠乏症 | 主な食品 |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 視力保持 皮膚、角膜の保護 抗酸化作用 | 夜盲症 角膜乾燥 皮膚の角化 | レバー、うなぎ あんこうきも カロテノイド:緑黄色野菜 |
| ビタミンD | 骨、歯の形成 | クル病 骨軟化症 | 鮭、キクラゲ あんこうきも しいたけ |
| ビタミンE | 抗酸化作用 細胞膜の安定化 血行促進 | 貧血 ・赤血球寿命の短縮 ・酸化的溶血(※)の亢進 | 植物油、魚介類 種実類、かぼちゃ アボカド |
| ビタミンK | 血液凝固因子の生成 | 血液の凝固時間が遅れる | 納豆、葉野菜 |
(※)酸化的溶血とは、ビタミンEの不足により血液中のビタミンE濃度が低下し、細胞膜の脂質が酸化され、低出生体重児や乳幼児などは赤血球膜の抵抗性が弱まり、溶血性貧血を起こすことをいう。
【水溶性ビタミン】

水溶性ビタミンとは、水に溶けやすく、脂質に溶けにくい性質を持つビタミンで、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンCがある。
ほとんど体内で貯蔵されないので、毎食、食物から一定量を取る必要がある。
余分に撮った分は、尿中に排泄されるため、過剰症の心配は少ない。
ー水溶性ビタミン一覧ー
| 種類 | 主な生理作用 | 欠乏症 | 主な食品 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | ・糖質の代謝 ・神経機能の補助 | 脚気 神経障害 | 豚肉 うなぎ 玄米 大豆 そば |
| ビタミンB2 | ・糖質、脂質、タンパク質の代謝 | 成長障害 口内炎 口角炎 | レバー 魚介類 牛乳 納豆 卵 |
| ビタミンB6 | ・タンパク質の代謝 ・神経伝達物質の合成 | 貧血 皮膚炎 アレルギー症状 | 魚介類 レバー 鶏のささ身 バナナ |
| ビタミンB12 | ・タンパク質、核酸の合成 ・造血作用 | 巨石芽球性貧血(※1) | 魚介類 レバー |
| ナイアシン | ・糖質、脂質、タンパク質の代謝 | ペラグラ(皮膚炎) | 魚介類(赤身) レバー 鶏のささ身 落花生 |
| パントテン酸 | ・糖質、脂質、タンパク質の代謝 | 頭痛 疲労 免疫力の低下 | レバー 魚介類 納豆 牛乳 アボカド |
| 葉酸 | ・核酸の合成 ・造血作用 | 巨石芽球性貧血(※1) | レバー 緑黄色野菜 卵黄 |
| ビオチン | ・糖質、脂質、タンパク質の代謝 | 皮膚炎 脱毛 | レバー 卵 大豆 |
| ビタミンC | ・コラーゲンの生成 ・抗酸化作用 | 壊血病(※2) | 果物 野菜類 いも類 |
(※1)巨石芽球性貧血とは、ビタミンB12や葉酸が欠乏して、赤血球になる前段階の赤芽球が成熟できなくなって貧血を起こすことをいう。
(※2)壊血病とは、ビタミンCが欠乏して、コラーゲンの生成ができなくなって毛細血管が弱くなり出血しやすくなることをいう。
【その他のビタミン】

ビタミン様物質(ビタミン様作用因子)は、体内においてビタミンに似た重要な働きをするが、体内で合成されるため、欠乏症が起こらないという特徴を持つ。
ビタミン様物質は、生命維持のために摂取が必要というより、疾病予防や美容や健康の維持に役立つ有用な役割が注目されており、実際に医薬品として利用されているものもある。
ービタミン様物質一覧ー
| 種類 | 主な生理作用 | 主な食品 |
|---|---|---|
| オロット酸 (ビタミンB13) | ・葉酸、ビタミンB13の代謝促進 ・脂肪肝の予防 ・核酸の合成 | 根菜類 小麦胚芽 ビール酵母 …など |
| パンガミン酸 (ビタミンB15) | ・肝臓機能の改善 ・心疾患の予防 | かぼちゃの種 ごま ビール酵母 …など |
| リポ酸 | ・肝臓機能の改善 ・抗酸化作用 ・解毒作用促進 ・糖質の代謝 | ビール酵母 レバー …など |
| イノシトール | ・脂肪肝や動脈硬化予防 ・脱毛予防 | オレンジ すいか メロン もも …など |
| コリン | ・脂肪肝の予防 ・コレステロール値の改善 ・脳の老化予防 | レバー 卵黄 大豆製品 エンドウ豆 …など |
| パラアミノ安息香酸 (ビタミンBx) | ・皮膚や毛髪の健康保持 | レバー 卵 牛乳 玄米 …など |
| バイオフラボノイド (ビタミンP) | ・毛細血管の強化 ・抗酸化作用 | 柑橘類 あんず そば …など |
| ユビキノン (コエンザイムQ10) | ・酸素、エネルギーの供給 ・抗酸化作用 ・免疫機能を向上 | レバー 牛肉 豚肉 カツオ マグロ …など |
| カルニチン (ビタミンBt) | ・脂肪酸の代謝補助 | 肉類 魚介類 …など |
| キャベジン (ビタミンU) | ・消化性潰瘍の予防 | キャベツ レタス アスパラガス …など |
まとめ

たくさんのビタミンがありますが、体の機能維持に必ず必要になります。
スポーツをする中でも、例えばビタミンB1が不足すると、神経機能の補助ができなくなり、体のパフォーマンスが落ちる可能性があります。
またパントテン酸が不足すると疲労、免疫力が低下し、これも体のパフォーマンスが落ちる原因につながります。
ビタミンと言っても、たくさんの種類があり、いろんな食材から摂取する必要があります。
今一度、自分の体はちゃんと動けている?最高のパフォーマンスができる体になっている?
などと意識し、足りないビタミンを考えて見ることが、今後の野球のレベルを上げることに繋がっていくのではないでしょうか!
食事が体を作り、ビタミンは正常で健康な体を維持する!