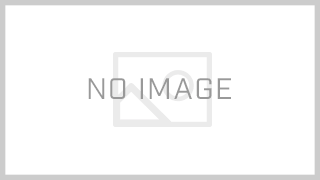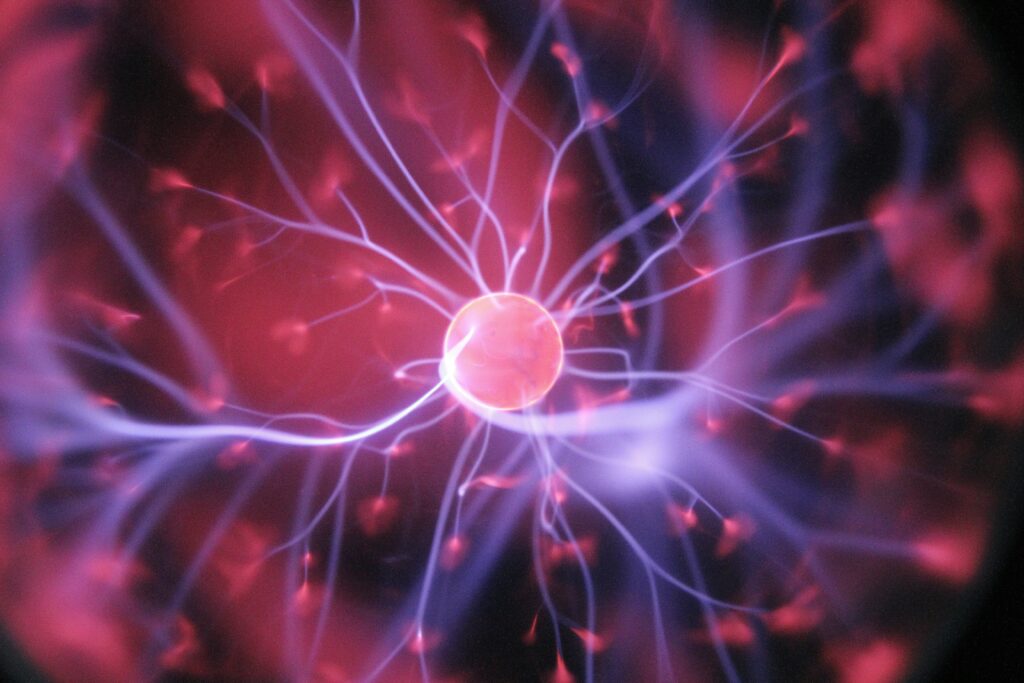
糖質は、主に生命を維持するエネルギー源として利用される重要な栄養素。
スポーツをする上でも、エネルギーはたくさん必要なので、糖質はしっかり摂取する必要がある。
糖質は、摂りすぎは体を壊す原因になりますが、きちんと糖質のことを理解し、摂ることで体に正しくエネルギー源になるので、今回は糖質の基礎を一緒に学んでいきましょう!
① 糖質の分類
② 糖質の特徴
まとめ
① 糖質の分類

糖質は、分子量の大きさから、単糖類、少糖類、多糖類の3つに分類できる。
単糖類は、糖質を構成する最小単位の物質で、糖質は単糖類まで分解され、体内に吸収される。
少糖類は単糖類が2〜10個結合したもの、多糖類はそれ以上の単糖類が結合したものである。
ー「単糖類」…これ以上分解できないー
| 主な種類 | 体内での主な働き・食品 |
|---|---|
| ブドウ糖(グルコース) | 血液中に血糖として一定濃度含まれ、 活動のエネルギー源となる。穀類や果物に多い。 |
| 果糖 | 体内で中性脂肪に変わりやすいため、 取りすぎは肥満、動脈硬化を引き起こす。 甘味が最も強く、果物や蜂蜜に多い。 |
| ガラクトース | 母乳や牛乳に含まれる乳糖の成分。 |
ー「少糖類」…単糖類が2〜10個結合したものー
| 主な種類 | 体内での主な働き・食品 |
|---|---|
| 麦芽糖 (ブドウ糖+ブドウ糖) | 大麦を発芽させた麦芽に含まれる。 水あめの主成分。 |
| ショ糖 (ブドウ糖+果糖) | サトウキビやてんさいに含まれる。 |
| 乳糖 (ブドウ糖+ガラクトース) | 整腸作用がある。乳汁中にのみ存在。 |
| オリゴ糖 (ブドウ糖、果糖、ガラクトース等) | 腸内のビフィズス菌を増やす。 大豆オリゴ糖、フラクトオリゴ糖などの 人工甘味料に含まれる。 |
ー「多糖類」…単糖類が10個以上結合したものー
| 主な種類 | 体内での主な働き・食品 |
|---|---|
| でんぷん | 穀類やいも類に多く含まれる。 |
| グリコーゲン | ブドウ糖が体内でつくり変えられたもの。 筋肉や肝臓に貯蔵されている。 |
糖質は種類によって、消化・吸収の速さが異なる。
【吸収速い】単糖類 → 少糖類 → 多糖類【吸収遅い】
例えば、ご飯に含まれる多糖類とケーキに含まれる少糖類で血糖値上昇が速いのは、単糖類の結合数が少ない少糖類である。
少糖類が多く入ったケーキを食べすぎた場合、血糖値は急速に上がる。
血糖値が急速に上がると、糖尿病などの疾患にかかるリスクが高まるといわれている。
一日に必要なエネルギーのうち、50〜65%は糖質から摂るのが望ましいといわれるが、そのほとんどをケーキなどのお菓子で済ませるのではなく、消化・吸収の速さが緩やかな多糖類、例えばご飯やパンを主食の中心に摂取するのが望ましい。
② 糖質の特徴

●体内での働き
糖質は、エネルギー源として最も重要であり、1g当たり約4kcalのエネルギーを産生する。
通常、優先してブドウ糖をエネルギー源として利用している脳や神経組織、赤血球などにブドウ糖を供給する。
また、糖質でのエネルギー摂取量を十分にすることでタンパク質がエネルギーとして使われることが抑えられ、タンパク質を体構成に使うことができる。
●多く含む食品
穀類やいも類、果物、砂糖などに多く含まれる。
| 種類 | 穀物 | いも類 | 果物 | 砂糖 |
|---|---|---|---|---|
| 食品 | ご飯 食パン うどん | さつまいも | バナナ | 砂糖 |
●過剰症
エネルギーとして直ちに利用されない場合、グリコーゲンに合成されて肝臓や筋肉に貯蔵されたり、中性脂肪となって貯蔵される。
そのため、糖質の取りすぎが続くと、肥満や脂肪肝の原因になる。
●欠乏症
糖質が不足しても、通常は糖質以外のエネルギー源であるタンパク質や脂質が分解されて充填される。
不足が続くと、脳や筋肉はブドウ糖をエネルギー源とするため、エネルギーが足りなくなり、体力は落ちたりする。
また、空腹時のエネルギー源となる筋肉や肝臓内のグリコーゲンが少なくなると、疲労感が強くなって、肝臓の働きが低下し、脳のブドウ糖が不足すると思考能力が低下する。
●効率よく摂取するには
糖質をエネルギーに変えるためには、ビタミンB群が欠かせない。
特にビタミンB1を摂取することで糖質の代謝が良くなる。
ビタミンB1を多く含む食材には、豚肉やうなぎ、玄米、大豆、そばなどがある。
まとめ

糖質は、体のエネルギー源として、運動する時には、一般の人よりエネルギーが必要なので、たくさんの糖質を必要とするが、糖質の種類を注意して、食べないと、運動のパフォーマンスに影響が起きてくる。
体に良い糖質の取り方を知り、運動をするときのパフォーマンスを最大限に引き出せるエネルギー源として、必ず食事でとることを意識してほしいと思います!